2025年夏山登山の第一弾として、上高地の小梨平キャンプ場にテント泊をして、焼岳に登ってきました。噴火により大正池をつくったことで有名な焼岳ですが、現在もあちこちからガスが噴き出したり、噴気孔から熱い蒸気が出ていたりと、火山の息吹を感じられる山です。山頂からの眺望も見事です!
上高地から焼岳へ日帰り登山
焼岳は、上高地の河童橋から穂高連峰と反対側に見える火山です。長野県と岐阜県の県境に位置する標高2,455メートルの火山で、日本百名山の一つにも選ばれています。
非常に活発な活火山で、2024年には地震が増加して登山中止の勧告が出ていました。2025年夏時点では比較的落ち着いているということなので、この機会に登ってきたというわけです。
今回は上高地から焼岳に日帰り登山です。歩いたルートは以下のとおりです。
焼岳の登山口は、河童橋を渡って梓川右岸の遊歩道を40分ほど歩いたところにあります。途中まではホテルが立ち並び、観光客も多いエリアですが、焼岳登山口のあたりは焼岳登山をする人しかいないので、とても静かです。
登山口から樹林帯を登り、中腹の焼岳小屋へ。焼岳小屋から先は樹林帯を抜け、火山らしい景観の岩がゴツゴツした斜面を登っていきます。
今回の主な行程は以下のとおりです。
- 05:55 小梨平キャンプ場 出発
- 06:35 焼岳登山口
- 08:10 焼岳小屋 到着(休憩)
- 08:30 焼岳小屋 出発
- 09:50 焼岳(北峰)登頂
- 10:50 焼岳(北峰)出発
- 11:45 焼岳小屋
- 13:10 焼岳登山口
- 14:00 小梨平キャンプ場 到着
今回は小梨平キャンプ場でテント泊をして、2日目に朝から焼岳に日帰りで登りました。小梨平キャンプ場から焼岳山頂のピストンで、距離13.7km、累積標高は1,066メートルでした。
距離と累積標高だけみればふだんの日帰り登山と大差ないですが、そこは北アルプス。後半のザレた急登がなかなかキツいです。一方で、火山らしさを随所で体験できる、歩いていて楽しいルートでもあります。
【上高地】小梨平キャンプ場から焼岳登山口へ
小梨平キャンプ場から5分ほどのところにある河童橋を渡り、梓川の右岸の遊歩道を南下します。途中にはホテルが立ち並ぶエリアもあり、早朝の散策を楽しむ観光客も多いです。観光客の姿が見えなくなると焼岳登山口です。
早朝の小梨平キャンプ場を出発
前日のお昼過ぎに上高地に到着し、小梨平キャンプ場でテント泊をしました。翌日、午前6時前にテントを出発。テントの目の前からは梓川と穂高連峰を眺めることができる最高のテントサイトです。
明神方面へと急ぐ登山者とは反対方向へ。今日は土曜日なので、穂高や槍ヶ岳を目指す登山客が多いのでしょう。午前6時の河童橋周辺にも観光客の姿がちらほら。朝食前の軽い散策といったところでしょうか?
河童橋の向こうには、これから登る焼岳の姿が見えていますね。
梓川右岸の遊歩道を歩いていきます。河童橋周辺の賑やかな場所を抜けると少し静かになりますが、すぐにホテルが立ち並ぶエリアへ。
公衆トイレをお借りしたあと、すぐ近くのウェストン碑へ。日本の名峰や上高地の魅力を世界に伝えた英国人宣教師です。
早朝の梓川。まだ人が少なく静かです。水はとてもきれいで透き通っていますね。
西穂高岳の登山口に到着。このあたりまでは観光客も歩く遊歩道になっているようですが、この先はあまり観光客はやってこないエリアのようです。
遊歩道からも焼岳の姿が見えました。なかなか迫力のある火山らしい山です。同じ上高地からアクセスできる穂高連峰や常念山脈とは違った趣のある山で、このあたりではある意味、独特の山容をした山です。
小梨平キャンプ場から40分ほどで焼岳登山口に到着。ここからいよいよ登山道に入っていきます。
【登山口~焼岳小屋】樹林帯を抜け長いハシゴを登って焼岳小屋へ
登山口からしばらくは樹林帯が続きます。傾斜は比較的緩いですが、風があまり通らずに蒸し暑いです。短いハシゴがいくつか出てくるあたりからやや傾斜が急になり、少し開けてくると、焼岳名物の長いハシゴへ。樹林帯を抜けて草地の斜面をジグザグに登っていくと、中腹にある焼岳小屋に到着です。
蒸し暑い樹林帯をクマにおびえながら登る
最初はほぼ平坦な樹林帯を歩いていきます。もちろん自然林の森ですので暗くはありませんが、このあたりはクマの目撃情報が多いそうなので、熊鈴を鳴らしまくりながら、早足で登っていきます。
しばらくすると次第にのぼりがでてきますが、まだまだ歩きやすい樹林帯の道が続きます。歩きやすいのはいいのですが、他に誰も登山者を見かけないので、ちょっと心細いですね……。クマに遭わないことを祈りつつ登ります。
だんだん傾斜が急になっていきます。それでもたいしたことはないのですが、蒸し暑いのでかなり汗をかきます。上高地からの登山ということで、もう少し涼しいのかと思っていましたが、そんなこともないようです。
連続する短いハシゴを登る
まだ樹林帯が続きますが、登山道には短いハシゴがたくさん出てきます。ハシゴの上り自体は特に問題ありませんが、そのぶん傾斜も急になってきていますので、慎重に登ります。
大きく崩れた崩壊地。火山のせいなのか、火山ゆえにもろい地質なのか。大きくえぐれた谷を風が吹きあがってきて、心地よいです。少し景色を眺めながら涼みました。
ハシゴのような橋を渡ります。
ここまで、特に危険そうなハシゴはありませんでしたが、このハシゴは一部の段が破断していてテープで補修されていました。強度を確認しながら慎重に登りました。(とりあえず強度は大丈夫そうでした)
焼岳名物の長いハシゴ
短いハシゴが続くエリアが終わると、樹林帯から抜けて、目の前に焼岳の迫力のある姿が見えてきます。先ほど目の前にみえた深い谷間が山頂付近から続いていることがわかります。
この深い谷間は、ガリー(雨裂)と呼ばれるもので、2300年前の噴火で堆積した砕流堆積物が、その後の雨水浸食や小さな崩壊を繰り返すことで作られたものなのだそうです。
日の当たるところに出てきたためか、樹林帯の中にはほとんどなかった高山植物が登山道脇に目立つようになります。
例の長いハシゴです。このハシゴは、雪崩などで破損することを防ぐため、冬季には取り外されてしまいます。毎年、取り外しをしているということですね。
なかなかの長さがあるのと、何というか、ふつうのハシゴをいくつか連結して架けたような姿に少し不安を感じます。が、実際に登ってみるとかなりしっかり固定されているので、強度的にはまったく心配ありませんでした。
上りきってから下を見てみると、本当に垂直ですね。帰りはこれを降りないといけません。降りる方が断然怖そうです……。
樹林帯を抜けて焼岳小屋に到着
先ほどの長いハシゴのすぐあとに、鎖場が2つ続いています。難しくはありませんが、慎重に登っていきます。
鎖場を抜けると、樹林帯から出て、目の前に焼岳の迫力のある姿が飛び込んできます。中央の少し出っ張っている大きな岩が山頂です。
山頂付近に雲が流れてきたり晴れたりを繰り返しています。山頂に着くまでガスが上がってこないと良いのですが。
登山道は、中腹の斜面をジグザグに登っていく形になります。樹林帯から抜けて、笹の道になります。強い日差しが容赦なく照りつけますが、風が少しあるので涼しく感じますね。標高が上がってきたせいでしょうか。
8時15分、焼岳小屋に到着! 少し谷間になった樹林帯の中にある小さな小屋です。
実は、暑さのせいか、ここまででかなりバテてしまっていました。焼岳小屋でポカリスエットを買い、持参したパンを食べながら少し長めの休憩を取りました。ポカリスエットが効いたのか、涼しい日陰で休んだためか、幸い体調はすぐに回復し、このあとはいつも通りのペースで歩くことができました。
火山であることと、この先はガレ・ザレの道が続くことから、ここでヘルメットをかぶることにします。
【焼岳小屋~焼岳】変化に富んだ火山らしい景色を堪能しながら山頂へ
焼岳小屋からは、これぞ火山と思わせてくれるような景観が続きます。景色だけでなく、熱い蒸気が噴き出していたり、硫黄の匂いがしたりと、五感で火山を楽しみながらの登山になります。
小ピークから眺める迫力ある焼岳
焼岳小屋から少し歩くと、すぐに樹林帯を抜けて、目の前に焼岳を見ながらの登山となります。先ほどと変わらず、焼岳の手前にガスの通り道があるのか、ガスに覆われたり晴れたりを繰り返しています。
焼岳小屋から10分ほどで、見晴らしの良い小ピークに到着しました。目の前にはどーんと迫力のある焼岳が聳えています。登山道はどこにあるのだろうと目を凝らしてみると、どうやらほぼ直登のようです……。
この小ピークの脇には、熱い蒸気が噴き出る噴気孔がありました。風が吹くと冷たくて気持ちの良いところですが、この噴気孔からの蒸気だけは明らかに温度が高いです。
小ピークの周辺には、黄色の花が咲き乱れるお花畑がありました。噴気孔のおかげで周囲の温度が高いからでしょうか、今回のルートでは、この周辺が一番高山植物が多かったですね。
中尾峠から草地の登山道を登り返し
小ピークから少し下ったところ、小ピークと焼岳の鞍部が「中尾峠」です。新穂高温泉側の登山口から登ってくると、この中尾峠に出るようです。
中尾峠からは再び登りに。背の低い草地の中の登山道を登っていきますが、まだ傾斜は緩く、快適に歩けます。
途中で振り返ると、梓川と上高地、その奥に穂高連峰の稜線が見えるようになってきました。だいぶ標高が上がってきたということでしょう。左側に見える丘のような山が、先ほど通ってきた小ピークです。
草地の道が終わり、岩とザレの道へ。これまでの道と違って、登山道がわかりづらいところもありますが、岩にペンキで〇や矢印がかかれているので、それを目安に登っていきます。
ガレた岩の道を直登して山頂直下へ
このあたりは岩や石が多い道になります。浮石も多く、登山者が落とす落石もちょくちょくあり、慎重に登っていきます。焼岳は火山だからということでヘルメットを持っていきましたが、このガレた道の落石対策にもなりました。
山頂の大岩の下まで登ると、今度はその大岩を左から巻くように、大岩の壁の下を歩いていきます。頭上には垂直に切り立った大岩が聳えています。おそらく噴火の時の溶岩ドームが固まったものではないかと思いますが、今にも崩れてきそうでちょっと怖いですね……。
山頂をつくる大岩の下までやってきました。山頂に人がいるのが見えますね。最後は、この大岩を登っていきます。
硫黄のガスが噴き出す大岩を登って焼岳山頂に到着!
そんなことはないのでしょうけれど、今にも崩れ落ちてきそうで怖いですね……。
大岩の中腹からは、激しくガスが噴き出しています。周囲が黄色くなっていますし、硫黄の臭いがするので、硫化水素のガスが噴き出しているのでしょうか。焼岳が火山であることを実感させてくれる光景です。
午前9時50分、焼岳(北峰)に登頂! 小梨平キャンプ場から約4時間で登頂できました。
焼岳山頂からの絶景を満喫!
山頂で休憩しながら景色を楽しみましょう!
東側には上高地と梓川。左側の絶壁のように高い山は穂高連峰ですね。その奥は蝶ヶ岳あたりの常念山脈の稜線でしょうか。
大正池もバッチリ見えますね。1915年、この焼岳の噴火で梓川が堰き止められて、大正池が誕生しました。
西側には、すぐ下に池があります。焼岳の北峰と南峰の間です。火口湖のようですが、大きさ的には「池」ですね。
その先には、焼岳のもう一つの山頂、南峰が見えています。あちらは崩落しやすいということで、現在は立ち入り禁止になっています。左奥の雲間にちらっと見えるのが乗鞍岳。その下の登山道は、中ノ湯からの登山道です。
焼岳は、上高地からのぼるより、中ノ湯のほうからのぼる人のほうがずっと多いようです。上高地の登山口から山頂まで、途中で見かけたのは数人~10人程度でしたが、山頂はずっと多くの人で賑わっています。みなさん、中ノ湯のほうから登ってきたのでしょうね。
山頂は雲に隠れてしまっていますが、西穂高岳も見えています。左下に先ほど通ってきた小ピークと、谷間に青い屋根の焼岳小屋が見えます。その尾根筋をずっと登っていくと西穂山荘に着くようです。焼岳小屋でも、テント泊装備をデポして焼岳を往復した後、西穂山荘を目指すという若者グループがいました。
北側の谷間に見える集落は、岐阜県側の新穂高温泉でしょうか? 焼岳は、穂高連峰と同じく、長野・岐阜県境にある山なので、岐阜県側の街並みを見渡すこともできます。
予定していたよりも早く登頂できたので、山頂でゆっくり過ごしました。およそ1時間、景色を眺めながらのんびりできました。
【焼岳~小梨平】ピストンで上高地に下山
10時50分頃に下山開始。山頂の大岩を慎重に下り、ガレ気味の道を下っていきます。傾斜が急で、浮石も多めなので、滑らないように慎重に下っていきます。
とりあえず、焼岳小屋を目指します。眼下に、青い屋根の焼岳小屋が見えていますね。
1時間ほどで焼岳小屋まで下ってきました。ここで小休止。トイレをお借りし、水を汲みました。
焼岳小屋から少し下ると、例の「長いハシゴ」があります。やはり下りは恐いですね。最初に足を架けるのもかなり怖いですし、下っているときも、どうしても下を見ざるを得ないので、少し足がすくみました。技術的に難しいものではないので、この恐怖に打ち勝って冷静に下れるかがポイントですね……。
長いハシゴを下ったあとは樹林帯に入り、景色も見えなくなるので、黙々と下ります。下りとはいえ、風が通らない樹林帯はとても蒸し暑く、ちょくちょく水分補給をしながら下っていきます。
山頂から2時間ちょっとで登山口まで下ってきましたが、ここから小梨平までがまだ長いのですよね……。
小梨平に戻ってからお昼を食べようと思って急いでいましたが、上高地温泉ホテルの売店が開いているのを見て立ち寄りました。ソフトクリームを売っていたので、購入して小休止。朝と違って観光客の数も多く賑わっていました。
ソフトクリームでリフレッシュしたので、帰路は梓川沿いの遊歩道を歩いてみることにします。河原に下りてみると、なんと美しい川面の色! 見るからに涼しげですが、日なたはかなり暑いです。
日なたは暑いので、爽やかな森の遊歩道へ。吹き抜ける風は心地よいですが、それでもやはり暑いですね……。避暑地とはいえ、夏は暑いのです。
14時少し前に河童橋まで戻ってきました。晴天の土曜日ということもあって、すごい人! 穂高連峰もきれいに見えていて美しいですね。
14時過ぎに小梨平キャンプ場に到着。テント前からの景色も見事! …ですが、小梨平キャンプ場のお風呂の入浴時間が始まっているので、さっそく汗を流してきました。
入浴後は、売店で缶ビールを購入して乾杯! テントもかなり増えていて、にぎやかになっていましたね。
火山らしい景観を楽しめる日帰り百名山「焼岳」
上高地から日帰りで焼岳に登ってきました。
2024年は火山活動が活発で、松本市から登山の自粛を求める通達が出ていたので登れませんでしたが、今年2025年は比較的落ち着いているようです。
それでも、やはり活動が活発な活火山で、焼岳小屋から上では、随所に火山らしい景観を見ることができました。あちこちから噴き出す噴気や、触るとほんのりと暖かい岩などは火山ならではですね。
山頂からの眺望も抜群! 標高2,400メートル台と、周囲の山々と比べると一段低いのですが、焼岳自体が独立峰的に周囲の山並みから少し離れているので、360度の眺望を楽しめました。
上高地からは日帰りで登れるので、キャンプや観光とあわせて焼岳の登山を楽しむのがおすすめです。
今回の主な登山装備
今回は小梨平キャンプ場でテント泊しながらの登山でした。焼岳登山は日帰りなので、テントを張ったまま、不要なものはテントに置いて行きました。
- ウェア類
- アンダーレイヤ: モンベル ウィックロンの半袖Tシャツ
- ミドルレイヤ: モンベル 化繊 長袖シャツ
- 防寒着: モンベル ライトシェルパーカー(ソフトシェル)
- パンツ: ノースフェイス アルパインライトパンツ
- レインウェア上: モンベル レイントレッカージャケット
- レインウェア下: モンベル サンダーパス パンツ
- 靴下: フィッツ メリノウールの登山用靴下
- 登山靴: モンベル アルパインクルーザー2300
- 登山補助
- 膝サポータ ザムスト EK-3(両膝)
- ヘルメット
- 緊急用
- ファーストエイドキット
- ヘッドランプ、予備の電池
- ザック: ミレー サースフェー 40+5 (45リットル)
- 水
- ナルゲンボトル 1リットル
- ペットボトルの水・お茶 0.5リットル×2本
序盤、登山口から焼岳小屋までは、とにかく蒸し暑く、早々にバテ気味になってしまいました。バテてくると水の消費量も増えますね。結局、持参した2リットル+焼岳小屋で購入したポカリスエット1本を消費しました。
バテてしまった原因はよくわかりませんが、熱中症や脱水症状ではなく、ミネラル不足かもしれません。持参したのはすべて水とお茶でしたが、焼岳小屋でポカリスエットを購入して飲んだらすぐに良くなりました。いつもはナルゲンボトルにポカリスエットを作って持っていくのですが、今回に限って水をそのまま持って行ってしまったのが失敗かもしれません。
猛暑が続く夏山登山。水分量だけでなく、飲み物の種類も重要ですね。
また、今回はヘルメットを持参しました。実際に登ってみると、火山であるということ以前に、上部のガレ気味の登山道では浮石が多いので、落石対策としても役に立ちました。
以上、「【焼岳】上高地から焼岳へ、火山を五感で楽しむ日帰り登山!」でした。近くにある槍・穂高連峰や常念山脈などの山とは一味違う、火山らしい景観を味わえる焼岳。上高地観光とあわせて登ってみてはいかがでしょうか?























































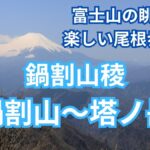

コメント